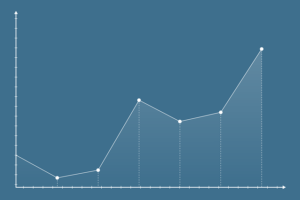手
手
夕陽へ向かう電車の中、女の手を見ていた。
窓際に座る、若い女の手だった。
「今さっき月を砕いてきたの」と手は語った。
それほど、白く、強く、内側から光っていた。
トクトクと拍動つ青い血管は、私の本能を刺戟した。
手は、時を止めながら自分だけ息づいていた。
――― 良い聖母になるかもしれない。
それとも、もうそうなのかもしれない。
夕陽に照らされ、手はいよいよ美しい。
美しくあろうとしているわけではない。
その手に邪な意思はない。
愛は美しいのか、美しいから愛なのか
そんなこと、手は気にしていない。
子供の頭に
夫の背中に
月の破片やら愛やらを埋め
与え続け、
与えられ続け、
果ては聖母の手かもしれない。
一番幸福な手かもしれない。
―――ところで、私の手は鉄の匂いがする。
感情を殺してきた匂いがする。
見えない血に濡れた手 ―――。
目をつむり、腕組みをしたまま
私は、白い月が赤く汚れるのを想った。
作:知伊田月夫